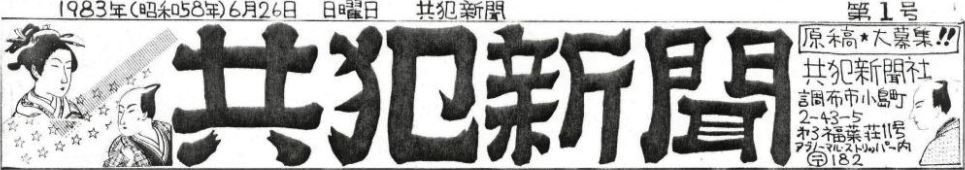
★ Guest Book from your brain ★
◆ 脳味噌は、「コトバ」の溶鉱炉!◆
ユートピア的であるがゆえに論争的な
初代2001年4月7日
~2004年10月4日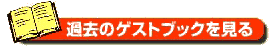 |
2代目2004年10月10日
~2011年6月25日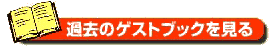 |
3代目2011年6月25日~2022年4月26日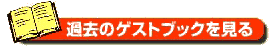 |
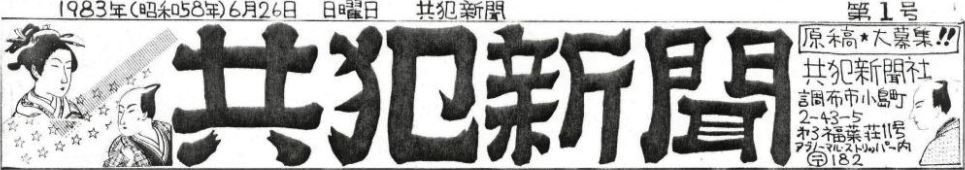
初代2001年4月7日
~2004年10月4日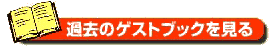 |
2代目2004年10月10日
~2011年6月25日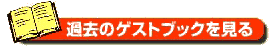 |
3代目2011年6月25日~2022年4月26日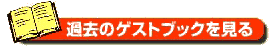 |
『共犯新聞』4代目ゲストブック♪
吉本隆明による架空追悼憑論「渋谷さんが泳いだ海」 - 中野真吾
2025/09/26 (Fri) 22:27:12
渋谷陽一さんをロック評論家と呼ぶこともアグレッシブな経営者と呼ぶことも、あるいは一風変わった形での市民運動家と呼ぶこともできるだろうが、ここではただ私の年少の友人とさせてもらいたい。渋谷さんが私の仕事を熱心に追ってくれたほどには私は渋谷さんの仕事を追っておらず、その価値も限界も、きちんと認識できていない自覚がある。私はあの独特な風貌が微笑みながら語りかけてくれる、その直接の接触から得た感覚を通じて、渋谷さんの仕事を思い返してみたい。
私がザ・スターリンやRCサクセション(遠藤ミチロウや忌野清志郎と言ってもいい)について語ったのは間違いなく渋谷さんの示唆があったからだ。素人の私がとは思わなかったものの、門外漢だという気持ちは離れなかった。彼らの仕事の水準の高さは疑わなかったが、太宰治や鮎川信夫に触れたときのように喰い込まれることはなかった。彼らについて語りながら、俺は所詮、彼らの歌詞についてしか語ってないよなあという思いは離れなかったし、音としての声と意味を持たざるを得ない歌詞との関係や、それが電子楽器の音やリズム、観客の声に飲み込まれて行く時の戦慄については、語る端緒もつかめなかったという他はなかった。
先日、ロッキング・オン誌に掲載された渋谷さんの追悼特集を読んだ。彼の旧友や後輩編集者の語る思い出話はそれぞれに感動的だったが、それ以上の何かではなかった。加えて紙面のどこにも渋谷陽一的思考が残っていないことに、しらじらとした思いをさせられた。結局のところ私が惹きつけられたのは、再録された渋谷さんの古い原稿だった。
「海には出たけど泳げない」の中で渋谷さんは次のように語っている。「優れた音楽批評は、優れた文学作品であり、それは当たり前の事だが、優れた音楽作品ではない」「批評は批評として自立しているのだ。しかしそれは文学としての自立であり、音楽批評という特殊な表現ジャンルが自立して存在するわけではない。言ってしまえばきっかけがたまたま音楽だっただけで他の何かであってかまわないわけである。だが僕にとって音楽は、他の何かであってはならない。それは音楽でなくてはならないのだ」「音の高さと長さのつながり。それが人の情動を刺激し、悲しいとか、嬉しいとかいった気分を喚起する。その反応は普遍的とさえいえる。一体何故なのか。音楽批評は、その第一歩ともいえる質問に対し何ら答えていないし、また答えようともしていない」「音楽を文学的論理で語るのでなく、音楽そのものの論理で語る、それができない限り音楽批評はその自立性を獲得する事ができない」
これらの言葉を読むと、43年前に渋谷陽一が直面していた課題が何一つ手を付けられることなく今も存在していることがわかる。ある面、私の抱えてしまったやりきれない感覚がそのまま残っているとも思えるのだ。
渋谷陽一のロック評論について言えば、それは大きく二つの柱を持っている。一つは「ロックは演奏者の飢餓感と時代の無意識とを反映して従来の自己を否定し変革していく」という表現論であり、もう一つは「いまここにない音楽を聞きたいという欠乏感を持った者たちが選び取る音楽は、必ず時代の無意識を反映し、メインストリームを形成する」という受容者論である。
大雑把なところでは妥当だと思うものの、それはあくまでビートルズのような稀有な一例についての分析であり、ロックの全てを貫通する理論にはなり得ていないのではないかと思わずにはいられなかった。ロックはつまるところ全世界を覆った大衆芸能であり、国家や資本、さらにいまや国家以上の権力を持つかもしれない大衆言論と対峙する中では、さまざまな身ぶり、反語、韜晦などを経由せざるを得ず、したがって彼らが提出した作品や語っている言葉は、必ずしも真に受けることはできないのだ。それは私には自明なことに思える。
しかし渋谷さんは、最後までその観点には一顧もくれなかった。気付かなかったはずはなく、そこには何かの理由があったに違いないのだ。
後輩の編集者が書いているように、渋谷さんは根っからのロック狂であった。おそらくロックと銘打たれる音楽のすべてが彼の興味の対象だったし、ロックの領域をかすめているもの、ロックから派生したもののすべてが彼にとってはロックだった。
ここからは完全に推測になるが、渋谷陽一理論に適合しないロック作品の中にも渋谷さんの好きな音楽はいくつもあり、しかし渋谷さんはそれについて完全に沈黙した。あるいは語ることを潔しとしなかった。追悼号に掲載された渋松対談の中で渋谷さんは「上手に年をとる」ことを否定し、「ロックっていうのは結局、初期衝動を肯定していくしかない音楽で、そこと上手に距離をとっていってはロックそのものを否定してしまうような気がする」と語っている。さらに「善意が有効だと思っている限り、ロックな心は生まれない」とも語っていて、私にはこれこそが渋谷陽一のロック宣言だと思える。
渋谷さんは自らの青年初期に熱中した音楽と、そこで受けた衝撃を分析し「初期衝動」という言葉を与えた。初期衝動は名前のとおり次第に減衰していくが、次々に現れる若者たちが必ず新たな初期衝動を持つことを信じ、それに応える音楽をロックと呼んだ。どんなに完成した音楽でも、鍛え上げられた作品でも、青年の初期衝動に無縁なものをロックと認めなかった。それとともに、減衰しない初期衝動があり得ることも信じようとした。おそらく渋谷さんは、最初の初期衝動を持ち続けるとともに、次々に現れる「ロック」に反応できるよう、最初の初期衝動を更新し続けようとした。
渋谷さんは前述の文章で、音楽批評の道を切り拓くことを海を泳いで目的の地までたどり着くことになぞらえている。現役のロック評論家のまま突然の病に倒れた姿は、泳ぎながら力尽きたと言えなくもない。目標地点のどのあたりまでたどり着いていたのか、泳いだ方向に目指すものはあったのか、泳ぎ続けたらどこにたどり着けたのか誰にもわかりようがない。しかし渋谷陽一が泳いだのはそのような海であり、彼がその海を誰よりも遠くまで泳いだということだけは疑えないのだ。
吉元隆明『ロックにとってビートルズとはなにか』第Ⅰ巻 - 久保AB-ST元宏 URL
2025/10/04 (Sat) 12:14:03
 ロックとはなにかを問うとき、わたしたちはビートルズをふまえたうえで、はるかにとおくまでロックの本質へゆきたいという願いをもっている。
ロックとはなにかを問うとき、わたしたちはビートルズをふまえたうえで、はるかにとおくまでロックの本質へゆきたいという願いをもっている。
2025年8月30日(土曜日)の朝日新聞で、スージー鈴木が渋谷陽一への追悼として、唯物論的な評論としての音楽そのものの「構造分析」に「情報業」の先を期待している と嘯いた程度のロックの解剖理論がわたしたちの最終の目的ではなく、たんなるはじまりであり、ロックの表現理論が最終の目的であるばあい、この欲求はやみがたいものである。
と嘯いた程度のロックの解剖理論がわたしたちの最終の目的ではなく、たんなるはじまりであり、ロックの表現理論が最終の目的であるばあい、この欲求はやみがたいものである。
https://keijibankako.web.fc2.com/yukigassen2025-0831.htm#n
そこで、わたしたちはロック評論家が終わったところからはじまり、ロック評論家は、わたしたちが終わったところからはじまるという関係が成り立つだろう。わたしたちはロックの塊を駆使した経験をもっているが、ロックを解剖したことはない。ロック評論家は解剖の経験を持っているが、ロックの塊を駆使したことはない。そこでロックの実証的な探索と解析は評論家たちにまかせ、ただその精髄を手に入れようとすれば、どこかでロック体験を交換しなければならない。もしうまくいけば、わたしたちはロックの塊と理論とをふたつとも つかむことができるはずである。
つかむことができるはずである。
渋谷陽一の「海には出たけど泳げない」につぎのようなところがある。
「音の高さと長さのつながり。それが人の情動を刺激し、悲しいとか、嬉しいとかいった気分を喚起する。その反応は普遍的とさえいえる。一体何故なのか。音楽批評は、その第一歩ともいえる質問に対し何ら答えていないし、また答えようともしていない」「音楽を文学的論理で語るのでなく、音楽そのものの論理で語る、それができない限り音楽批評はその自立性を獲得する事ができない」
ロックの最初の音声は伝達の用をなし、性欲の相手を呼び寄せた。ブルーズは労働作業に伴って発達した。つまり、既成のロック史にあるようなブルーズの発展形がロックなのではなく、クラッシック音楽やジャズ、フォーク、ラップ、民謡などのすべての表現の最初にロックがあるのだ。そこに文学や舞踊や映画や建築や数学などの表現の末裔をすべて含めてもいい。
ではなぜロックがまるで非嫡出子としての末っ子のように音楽史の最終ページに書かれたり、書かれなかったりする逆転が起きたのだろうか。それは、 ビートルズという表出回路を得てしまったからだ。ビートルズは永遠に新鮮である、と愚かなロック評論家は書くだろうが、ロックこそが人類史上もっとも古い表現であり、それをもっとも整理したのがビートルズだったのだから、むしろビートルズは新鮮である前に懐かしい存在であり、だからこそ全体を把握できない評論家には、それが新鮮に感じてしまうのだ。
ビートルズという表出回路を得てしまったからだ。ビートルズは永遠に新鮮である、と愚かなロック評論家は書くだろうが、ロックこそが人類史上もっとも古い表現であり、それをもっとも整理したのがビートルズだったのだから、むしろビートルズは新鮮である前に懐かしい存在であり、だからこそ全体を把握できない評論家には、それが新鮮に感じてしまうのだ。
まず、すべての表現技術が誕生する以前の状態を原始と定義しよう。そのうえで原始および原始的な音声は、いわば個々の感情的な体験を生理的感覚の機能にしずめこむとともに、共通の感情的な体験を、個々の祭式や集団行動の場面から抽出して象徴と表示に転嫁させる。つまり、渋谷陽一を葬るときにロックの詩の重視で足踏みを続けている場合ではなくて、 むしろ音の言語化こそが原始でありロックであると認識すべきである。
むしろ音の言語化こそが原始でありロックであると認識すべきである。
そのとき、ビートルズは優秀に機能したのだ。蛇足ながら、ビートルズがモーツァルトやシュトックハウゼンなどから影響を受けたのではなくて、ビートルズが人類史の最初の表現であるロックを整理しただけなのだ。だからこそ、ビートルズを人類は受入れ、それを『共犯新聞』は「売れ線」と表現しただけだ。
https://keijibankako.web.fc2.com/rock-shibuya-youichi2025-0714die.htm
ここまでの議論は、勘違いをしている多くのロック評論家向けに初心者向けレクチャーをしたのにすぎない。重要なのは、では、ビートルズにとってロックとはなにか、である。
ロックを媒介として世界を考えるかぎり、わたしたちは意味によって現実と関係し、たたかい、他の関係にはいり、たえずこの側面で、変化し、時代の情況のなかにいる。ただし意味は必要悪ではなくて、ロックが薄くなると法や国家や宗教などが代替えをするレイヤーの発生によってセクト化するだけだ。そしてセクトは自己保存のために固定をめざし、他セクトとの対立を生み、対立こそが生存理由であるかのような幼稚な逆説を唱え始める。
ロックを一部の切り取りにより文学や音楽理論などの狭いジャンルへ閉じ込める者は、ロックを塊として把握できていないだけだ。スージー鈴木が渋谷陽一を「ロックの文学化」と批判するのならば、わたしたちは同じ理由でスージー鈴木を「ロックの音楽理論化」と批判できる。コード進行と、音のひずみと、髪形などが塊となって存在しているのがロックだ。それが原始なのだから、当然だ。
ロックはゆがんだセクトに対立をやめろ、とか多様性の時代だ、とかは言わない。ただし、時代が聞く耳を持たないときロックは爆音を鳴らし、時代が安っぽい平和に安住するときロックはセンチメンタルにすねる。それらのとき、ロックは時代のリセットのスイッチのように登場しつつ、大きくスライドを見せ、可能性のうずを見せびらかす。たとえば、ビートルズがそうであったように。渋谷陽一が はみ出すことで同心円の透明な中心を浮かび上がらせたように。
はみ出すことで同心円の透明な中心を浮かび上がらせたように。
ロックがわからない例がおしえるものは、逆にロックという概念がじつにたくさんのものを包括しなければならないということである。
架空冥界放送「渋谷陽一の死人はつらいよ」 - 中野真吾
2025/11/03 (Mon) 16:55:07
(ひつこいようですが、こんなの書いてしまいました。ご笑覧ください)
お久しぶりです、渋谷陽一です。
えー僕が死んでけっこう経ったんですが、ブログやノートを見るといまだに結構な人が僕について書いてくれていて、ありがたいなあと思っています。死んでしばらくの間、従来の活字ジャーナリズムでは僕についての記事が載ったりしていたものですが、わりと早い時期にそれもなくなってしまって、なんだよみんな冷てえなと思ったし、何より書いてあることを読んで、「この業界は何十年たってもアホばっかりだ」と思ったりしたわけです。ある面、僕がやって来たことは何だったのかという感慨もありました。
そこへ行くと、インターネットメディアでは本当に多くの人が自分の声で自分のこととして、僕やロッキング・オンやサウンド・ストリートについて語ってくれていて、ああやはり、自分のやって来たことは無駄じゃなかったんだと感激しています。
ただ、もう一歩進んで言わせてもらうと、それらの熱い文章を読むと、どこかに「いや~違うな~」という気持ちが出てきてしまうわけです。この間から「共犯新聞」というウェブサイトの本文や掲示板でも、久保さんとか中野さんとかいう人がいろいろ書いてくれているんですが、それを読んでもそんな気がします。言ってることはわかるけれど、それは僕には当たってないよ、という気持ちが起こってしまいます。
で、それはしかし無理のないことだとも思うので、今夜は少しそのあたりの話をさせてもらいます。
そういった文章を書いてくれている人にひとつ共通するのは、割と早い時期のロッキング・オンや僕のラジオ番組に触れていただいて、そこで激しい共振現象を起こした体験を持っているということだと思うんです。おこがましい言い方になりますが、その人にとってのターニングポイントみたいなものになったと言いますか、それをきっかけに自分も何かの行動なり表現なりをするようになった人達だと思うわけです。
ところで「自分もこういうことをやって行きたい」とか、もっと度が進むと「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていくと、ごく自然なこととして僕とは離れていくんですね。これは本当に必然と言うべきで、一人の人間が進んで行くごとにその人のいる場所は変わっていくわけです。僕自身もどんどん変わっていくし、僕と共振してくれた人自身も変わっていく。ずっと一緒にいて共振しあっているという方がむしろ例外であって、そのような美しい奇跡もあるとは思いますが、それはもしかして不気味なことかもしれないし、平凡に言えば進歩がないということかも知れないわけです。
むかし岩谷宏がロッキング・オンに「僕たちは出会うわけではない。ものすごい速度でみごとにすれ違っていくのだ」みたいなことを書いていましたが、これはまさに正論なんですね。
だからですね、かつて僕のやっていることに触れた熱い人たちは、僕がその場所かその延長線上にいるものと考えて、今の僕のことを理解しようとする。でも僕は位置も方向もすでに違っているし、その人たちの位置も方向も、たぶんその時点とは異なっているわけです。だからその人たちが僕について何かを書いてくれたとしても、それは僕にとっては「何か違う」ものにしかなりえないわけで、いわばどうしようもないことなんですね。そもそも一人の人間が別の人間を完全に理解することがほとんど不可能なわけで、そう考えると「何か違うな~」と感じることがそもそもないものねだりじゃないかと言われたらその通りなわけです。
ただ付け加えたいのは、誰かを理解しようという気持ちは人間にとって最も切実なものの一つだし、僕を理解しようとしてくださる方の気持ちは本当にうれしいということです。
だんだん何を言っているかわからなくなってきましたが、僕たちは完全に分り合うことも一緒に進み続けることもできない存在で、しかし時には激しく理解し合い共振しあう存在であるということ、そのような奇跡は自分を開いてさえいればいつかまた起こりうるということ、そのことを実感を持って信じられる存在であること、つまり僕たちは孤独ではあるが希望にあふれた存在なのだと僕は考えています。
というところで僕よりもはるかに早く死んでしまった日本の偉大な表現者、忌野清志郎のうたを聞いてください。誰かが誰かを理解するということについて、非常に深いところで知っていた人だと思います。曲はRCサクセションで「君が僕を知ってる」。
吉元隆明『ロックにとってビートルズとはなにか』第Ⅱ巻 - 久保AB-ST元宏 URL
2025/11/05 (Wed) 02:09:48
 いままでで、ロックそのものから
いままでで、ロックそのものから じっさいのレコードへとりつくために必要な問題は、おおよそとりあげてきた。2025年8月30日(土曜日)の朝日新聞で、スージー鈴木が故・渋谷陽一をダシに、「唯物論的な評論としての「構造分析」」に「情報業」の先を期待した論法も、わたしは
じっさいのレコードへとりつくために必要な問題は、おおよそとりあげてきた。2025年8月30日(土曜日)の朝日新聞で、スージー鈴木が故・渋谷陽一をダシに、「唯物論的な評論としての「構造分析」」に「情報業」の先を期待した論法も、わたしは すでに、『ロックにとってビートルズとはなにか』第Ⅰ巻において、ロックを解剖理論と表現理論とに分けて整理し考察済みだ。
すでに、『ロックにとってビートルズとはなにか』第Ⅰ巻において、ロックを解剖理論と表現理論とに分けて整理し考察済みだ。
それでもロックの発生の原型をとりあつかおうと するとすぐに困難にぶつかることになる。たとえば、架空冥界放送「渋谷陽一の死人はつらいよ」のなかで、「「自分もこういうことをやって行きたい」とか、もっと度が進むと「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていくと、ごく自然なこととして僕とは離れていくんですね。」と述べている。重要なのは、渋谷陽一が離れていく未来では無くて、「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていく瞬間=今なのだ。それはビートルズの屍の向こうにセックス・ピストルズが屹立したり、セックス・ピストルズのパロディとして遠藤ミチロウが登場した後に、ビートルズやセックス・ピストルズが離れていっても、遠藤ミチロウの価値が変わらないのと
するとすぐに困難にぶつかることになる。たとえば、架空冥界放送「渋谷陽一の死人はつらいよ」のなかで、「「自分もこういうことをやって行きたい」とか、もっと度が進むと「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていくと、ごく自然なこととして僕とは離れていくんですね。」と述べている。重要なのは、渋谷陽一が離れていく未来では無くて、「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていく瞬間=今なのだ。それはビートルズの屍の向こうにセックス・ピストルズが屹立したり、セックス・ピストルズのパロディとして遠藤ミチロウが登場した後に、ビートルズやセックス・ピストルズが離れていっても、遠藤ミチロウの価値が変わらないのと 同じなのだ。
同じなのだ。
この論考は 久保AB-ST元宏が、すでに中野真吾が初めて『共犯新聞』に登場した
久保AB-ST元宏が、すでに中野真吾が初めて『共犯新聞』に登場した 3代目ゲストブックにこうかいている。
3代目ゲストブックにこうかいている。
中野さんの世代ですら、もうすでに早川義夫や斎藤次郎、真崎守は過去の人でしたよね。
でも、我らは、彼らにこそ同時代性を求めていたのかもしれません。
https://keijibankako.web.fc2.com/kyouhanshinbun-bbs2016-0612-2017-0224.htm#d
この引用は、現在、ロックの本質がどこにあるのかを一望するためのものである。スージー鈴木やマキタ・スポーツが渋谷陽一より年齢が現在に近いから「ここにもう一人の自分がいる」と感じたり、同時代であったり、ましてや正義であるはずもない。そうであれば、渋谷陽一が登場した当時、先行者の なかむらとうようを批判した理由が老若の問題に閉じ込められて安っぽくなる。
なかむらとうようを批判した理由が老若の問題に閉じ込められて安っぽくなる。
わたしは、ロックを記号として みずに、構造とみなしてきた。記号性はただたんにロックの構造に包まれて存在しうるだけである。しかし混乱は構造と像についておおくの不明瞭なものを残している。表現の構造は、
みずに、構造とみなしてきた。記号性はただたんにロックの構造に包まれて存在しうるだけである。しかし混乱は構造と像についておおくの不明瞭なものを残している。表現の構造は、 像の価値にはならないのだ。だからわたしはスージー鈴木の構造分析よりも、渋谷陽一が像を言語化しようとする包括的なロック存在論に加担する。
像の価値にはならないのだ。だからわたしはスージー鈴木の構造分析よりも、渋谷陽一が像を言語化しようとする包括的なロック存在論に加担する。
繰り返すが、 ビートルズは永遠に新鮮なのではない。ビートルズは「自分もこういうことをやって行きたい」とか、もっと度が進むと「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていくトリガーとして永遠に機能しているだけなのだ。その後、ビートルズが自分から離れて行ってもかまわない。なぜならば、ビートルズもビートルズから離れたのであり、渋谷陽一もしかりだ。雑誌『ロッキング・オン』2025年10月号は
ビートルズは永遠に新鮮なのではない。ビートルズは「自分もこういうことをやって行きたい」とか、もっと度が進むと「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていくトリガーとして永遠に機能しているだけなのだ。その後、ビートルズが自分から離れて行ってもかまわない。なぜならば、ビートルズもビートルズから離れたのであり、渋谷陽一もしかりだ。雑誌『ロッキング・オン』2025年10月号は 渋谷陽一・追悼特集号で売れたようだが、その翌月の11月号に渋谷陽一の名は目次の発行人名どころか、読者投稿欄にすら無かった。わたしが立ち読みしたのだから間違いない。がくっ。
渋谷陽一・追悼特集号で売れたようだが、その翌月の11月号に渋谷陽一の名は目次の発行人名どころか、読者投稿欄にすら無かった。わたしが立ち読みしたのだから間違いない。がくっ。
ロックにとってビートルズとは、永遠に出会える回路であり、同時に、自滅回路なのだ。
踏み出せば二度と会えなくなる道を、ぼくたちは歩き出すんだ - 中野真吾
2025/11/11 (Tue) 20:47:35
そうですね。
『「ここにもう一人の自分がいる」とか思った人が自分の道を切り開いていく瞬間=今なのだ』。しばらく前からぼくは、表現されたもの自体より、それを受け取った者の中で起こったことの方がすごいんだ!とか言っていて、あまり賛同も得られずにいるわけですが、大兄がそう言ってくださってうれしいです。
だいぶん前に磯田光一が「左翼がサヨクになるとき」の中で「中野重治や佐多稲子は間違いなく大日本帝国憲法と教育勅語が鍛え上げた最良の硬派なのだ」と書いていたのを読み、ずいぶん新しい視界を与えられました。
ところで今回同書を読み返してみたら、その文章が見当たらないのです。斜め読みして見逃しているのかもしれませんが、思い入れによる勝手読みが嵩じたニセ記憶かもしれません。
しかしもしそうなら、読み手の側に起こっていることも相当ですよね!
2025/11/12 (Wed) 10:11:24
 ふとTSUTAYA上江別店に行くと そこには雑誌『ロッキング・オン』2025年10月号が新刊なのに月遅れだからか2割引きでありました
ふとTSUTAYA上江別店に行くと そこには雑誌『ロッキング・オン』2025年10月号が新刊なのに月遅れだからか2割引きでありました
本当に何年ぶりのこと そこには渋谷陽一の追悼特集がありました
創刊からどの位たったのか 初めて読んでからどの位たったのか
ひとつ表現を受け取るごとに 批評は後に伸びていきます
悲しい毒ははるかな表現を染め 思い入れも勝手読みがニセ記憶としています
コンドーム一箱分の一月を 指でひねってごみ箱の中
僕は今 磯田光一『左翼がサヨクになるとき』を読み返し 30ページを読んでいるところ
「ここで私は、戦後文学のはらんでいる最大のパラドックスに直面せざるを得ない。「左翼」的と俗称される戦後派の文学とは、明治憲法と教育勅語の育て上げた世代の硬派な人格が、明治憲法と教育勅語のイデオロギーを果敢に批判した文学だったのではなかろうか。」
何もなかった事にしましょうと 今日も国会答弁が腐りました
あヽロックよ空を飛んで あの娘の胸に突き刺され
どこへ行くのかこの一本道 右翼もサヨクもわからない
聴けども聴けども聴き知らぬ新曲で これがロックというものかしら
踏み出せば二度と会えなくなる道を、ぼくたちは歩き出すんだ
レコードの穴からのぞいてみると そこには読み手の側に起こっていることがありました
表現と批評はホッペタを寄せあって 二人お酒をのんでました
その時『共犯新聞』が脳味噌へ配達されます もうすぐ夜が明けますよ
あれからどれくらいもたってはいないのに - 中野真吾
2025/11/13 (Thu) 12:38:30
そう、多分そこなんです。そこと241ページの「古典的な左翼に見られる〝節操固守〟の美徳は……〝農民の血〟のかがやきではなかったであろうか?」あたりをゴタマゼにして脳内で「生成」したものだと思います。「一本道」のメロディにのせていただいて、ありがとうございます。
大昔、「苺畑の午前五時」を読んだとき、仲間が全員逃げ出しす中、一人バリケードに残った主人公が「俺はビートルズを聞いてきたのだ。ジョン・レノンを聞いてきた人間なのだ。逃げることはできない」と考えるシーンがあると記憶し「アイデンティティとはこれなんだ!」と自分の中の名言録に加えておりました。
ところが何十年かたって読み返すと、そんなセリフもシーンもなく、父親の葬式で主人公がそれに近い語調でものを考えるシーンがあっただけで、さすがに驚きました。
もはや捏造ですな。