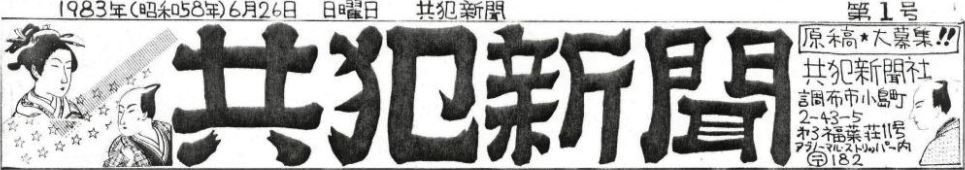
★ Guest Book from your brain ★
◆ 脳味噌は、「コトバ」の溶鉱炉!◆
ユートピア的であるがゆえに論争的な
初代2001年4月7日
~2004年10月4日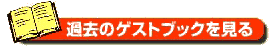 |
2代目2004年10月10日
~2011年6月25日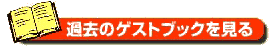 |
3代目2011年6月25日~2022年4月26日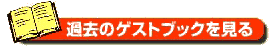 |
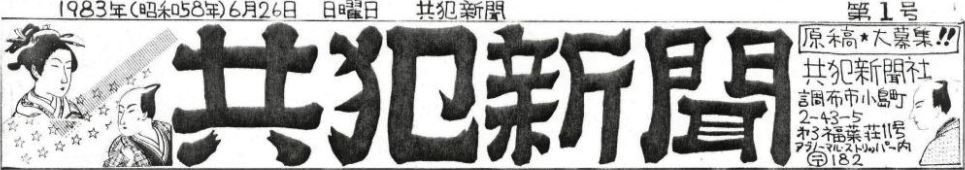
初代2001年4月7日
~2004年10月4日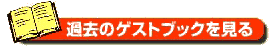 |
2代目2004年10月10日
~2011年6月25日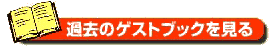 |
3代目2011年6月25日~2022年4月26日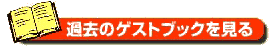 |
『共犯新聞』4代目ゲストブック♪
神谷宗幣の架空インタビューを読みたい - 中野真吾
2025/08/05 (Tue) 19:05:28
久しぶりに書き込みさせていただきます。
7月22日に渋谷陽一が死んだことを知り、それなりの感慨もあり大兄にメールを送ったり橘川幸夫のツイッターに胸をざわざわさせたりしながら、24日早朝から3泊4日の山登りに出かけました。山中ではネットを見ることもなく、帰りの電車でツイッターを見ましたが、橘川幸夫以外には書いている人は誰もおらず、サクバクとした気持ちになりました。
まあぼく自身も渋谷はもう難しいんだろうと思っていたし、実はもう死んでいるのに故人の遺志ということで発表せずにいるのでは…とさえ妄想していました。しかしそれにしてもみんな冷たいじゃないか、恩知らずばっかりだなとか自分のことは棚に上げてフンガイしておりました。
渋谷は「自らを否定し乗り越えて進化して行くものこそがロックだ」と言い続け、それを譲らないからこそ渋谷陽一なんだとは思いますが、その分ロック評論家~ロック紹介者としての渋谷陽一のリアリティは、ぼくにとっては薄くなっていました。ただあの声とあの語り口調はひたすら懐かしいです。渋谷には、あえて語ろうとはしないけれど本当は好きだった膨大な数のミュージシャンがいたはずで、あの声と口調でそれを語っていてくれたら、ぼくにとっての渋谷はもっともっと強烈な存在であり続けたのではとか思っています。
ところで、山から帰って来た夜、眠い目をこすりながら新聞を読んでいたら『参政党「躍進」の背景』という特集があり(しかし「躍進」のカッコ、嫌味ですね)、岡田憲治の「葛藤不在 心地よい押し活」という文章が印象に残りました。ぼくは「押し」とか「押し活」という言葉が大嫌いで、「なんでファンと言わないんだ、『押し』だなんてこっちに主体性があるみたいじゃないか」とか思っていたものですが、なるほど参政党支持が「押し活」であるというのはぴったりですね。ファンはめったなことで応援先を変えませんが(野球ファンを見ているとよくわかる)、押し活をしている人は割と簡単に変えることができるような気がします。今回参政党に投票した人のかなりの部分が、今までれいわに投票していたという話も聞きますし。
ちなみ以前知人が「なんで政治の話をすると喧嘩になってしまうんだろう」とぼやいていて、ぼくは「結局政党を支持することがファン意識で成り立ってるからじゃないかな」と思ったりしました。自分について言えば性格形成期のぼくは社会党ファンで自民党は打倒すべき敵、共産党は気に入らん奴らでした。いまは立憲民主にも国民民主にも社会民主にも腹が立つばかりですが、だからといって自民にも共産にも投票しようという気持ちには「ほぼ絶対に」なれません。ちなみに野球は横浜ファン、巨人は打倒すべき敵、阪神は気に入らん奴らです。
岡田憲治の文章に戻ると、それ以外に特に面白い部分はないなと思って読んでいたんですが、以下の数行にぐっと来ました。
『このイノセントな推しの主体には、紛れもなく「名付けられていない弱者」とも言うべき存在が含まれています。財務省前で減税を叫ぶ人と同じく「自分たちは政治から大切に扱われていない」という疎外感を抱えている。』
こういうのに弱いんですよ。「相手がハラスメントだと思えばその行為はハラスメントだ」という定義はむちゃくちゃだと思いますが、「ある人が疎外を感じるならその人は疎外されている」というのは正しいでしょう。
渋谷陽一が元気で参政党の躍進を知ったら、何と言ったでしょうね。
2025/08/06 (Wed) 17:27:08
 神谷宗幣「こんばんわ、
神谷宗幣「こんばんわ、 神谷宗幣です。」
神谷宗幣です。」
渋谷陽一「ちょっと、それ、私のパクリじゃね?」
神谷「いーんです。パクリの増殖こそが政治ですから。我が党は、 安倍晋三の軽い政治を
安倍晋三の軽い政治を 大阪維新の会の安易な手法でパクったおかげで、この度の参議院選挙で党勢を増殖させていただきました。」
大阪維新の会の安易な手法でパクったおかげで、この度の参議院選挙で党勢を増殖させていただきました。」
渋谷「だいたいね、君、選挙で 『政治はロックだ!』って叫んでいたって言うんじゃないの?」
『政治はロックだ!』って叫んでいたって言うんじゃないの?」
神谷「大手メディアも、『参政党の選挙集会はロック・フェスみたいだ』と報道していましたよ。弱小メディアの貴社も、是非、それをパクって いただきたい。」
いただきたい。」
渋谷「何言ってんだ。ロック・フェスは私の 飯のタネであって、
飯のタネであって、 ロックも
ロックも フェスも知らない似非ジャーナリストに気軽に使ってもらいたくない。」
フェスも知らない似非ジャーナリストに気軽に使ってもらいたくない。」
神谷「でも渋谷さんはその論理を若い時は、『文化現象というかムードとしてのロック風なものを、わけのわからない若者文化評論家という年寄りが書いたにすぎない。』と中村とうようなどの先輩に 毒を吐いていましたけれど、今や渋谷さんこそが『若者文化評論家という年寄り』いや、もはや
毒を吐いていましたけれど、今や渋谷さんこそが『若者文化評論家という年寄り』いや、もはや 『死体』でしょ(笑)。」
『死体』でしょ(笑)。」
渋谷「君ね、死体こそが究極の第三者なんだよ。そーゆー君は、ロックは何を聴いてきたんだい?」
神谷「バカにしないでください。私は、チェッカーズ第一世代ですよ、えへん。クラスで一番最初にチェッカーズ・ヘアーにしたのは私なのですから!それから、伝説のロック・バンド、BOØWYとか、Xジャパンに感動しました。あと、ちょっとマニアックですが、大事MANブラザーズバンドに私は生きる力をいただきました。このように私には、ロック魂が 根付いているのです。」
根付いているのです。」
渋谷「聞かなきゃ良かった。」
神谷「え?何か言いましたか?」
渋谷「ところであなた、 『ロッキング・オン』って知ってますか?」
『ロッキング・オン』って知ってますか?」
神谷「もちろんです。あれ、 マヨネーズに唐辛子を入れて喰うと美味しいですよね。」
マヨネーズに唐辛子を入れて喰うと美味しいですよね。」
渋谷「頭が痛くなってきた。」
神谷「いずれにせよ、長年、低迷してきた日本の投票率を 上げたのは我が参政党ですから、ロックの目指す参加型の政治、つまり参政党なのです。まぁ、昭和の
上げたのは我が参政党ですから、ロックの目指す参加型の政治、つまり参政党なのです。まぁ、昭和の 投稿型のエセ同人誌みたいなもんですよ(笑)。」
投稿型のエセ同人誌みたいなもんですよ(笑)。」
渋谷「・・・ああ、分かりました、はいはい。私、これからジョン・ボーナムのライブを聴きに天国への階段を昇りますので、あとはご自由にどうぞ。」
神谷「では、この場をお借りいたしまして、トランプ大統領、万歳三唱をご一緒に!」
渋谷「私が死んでからにしてください。がくっ。」
憑依?転生?パスティーシュ? - 中野真吾
2025/08/07 (Thu) 23:37:52
架空インタビューありがとうございます!
はじめは笑いながら読んでたわけですが、まるっきり渋谷陽一じゃないですか!語調といい用語といい、相手をまるっきりのアホに仕立てて貶めるやり口といい… わたしゃ泣けてきましたよ。「気軽に使ってもらいたくない」は、ぼくが会うことができなかったというか、知ったときには故人になっていた三宅【土人】伸也氏に捧げられた弔文中の一節の変奏ですね。
もう何も心配することはない。神谷が憲法改正して大統領になろうと、ロッキング・オンが統一教会に買収されて文鮮明の肖像が表紙を飾る日が来ようと、大兄がアンダーグラウンドで笑いものにしてくれる。これほど心強いことはありません。
架空インタビュー、「二代目シブヤソウルブラザーズ」とか偽名を使ってロッキング・オンに投稿しませんか!
2025/08/08 (Fri) 12:03:36
 渋谷「俺、最近、死んだんだけどさ。」
渋谷「俺、最近、死んだんだけどさ。」
中野「何だよ、いきなり。」
渋谷「おかげで腰痛とか、抜け毛が治ったよ。」
中野「・・・・・・。だからって、俺を誘うなよ。」
渋谷「お前を誘うのは、山男ぐらいだろ。」
中野「俺は、娘さんかっ。」
渋谷「しかし、天国はお前の好きな山よりも高いんだぞ。」
中野「お前が住んでいるのは、地獄じゃねーのか?」
渋谷「バカ言え。山の手のいーとこの坊ちゃんは、天国に行くに決まってるだろ。」
中野「坊ちゃんって歳かよ。」
渋谷「死んだら年齢はリセットすんだよ。」
中野「ふーん。そしたら、お前とジョン・レノンとジム・モリソンは同じ歳ってことか?」
渋谷「まぁな。時々、犬の散歩の途中でジョンに会うよ。」
中野「ジョンって名前の犬じゃねーのか?」
渋谷「・・・・・・。動物ネタで言えば、今朝はエリック・バードンに会ったぞ。どうだ?いいだろ。」
中野「お前、ほんとにロック評論家か?エリック・バードンはまだ生きてるぞ。どーせ、お前の評論は天国でも地獄でも評判が悪いから、ジミ・ヘンもジャニス・ジョプリンも近寄っては来ないだろーな。せいぜい、ソウル・イート時代を思い出して、松村雄策とシンナーでも吸ってろ。」
渋谷「しまった!松村雄策も、こっちに来てるんだ!忘れてたー。」
渋久架空対談 - 中野真吾
2025/08/08 (Fri) 16:08:47
渋谷「こんばんは、渋谷陽一です」
久保「うわびっくりした。なんだよ丑三つ時に」
渋谷「おれ登場はいつも夜だったと思うけど。それにお前いつもこの時間にHPいじってるだろ」
久保「だいたい顔が怖いんだよ。亡者のメイクなんてしやがって」
渋谷「失礼な。地顔だよ。死ぬかなり前からこの顔だぜ」
久保「そういやずっと前だもんな、お前をトークライブで見たの。あの時はかっこ良かったのにな。今じゃノーメイク亡者だな」
渋谷「これだって高齢リスナーに受けてるんだよ霊的だって。俺は現世でも来世でもリスナーに支持されてるぜ」
久保「それってリスナーの半分は鬼籍に入っているってことじゃねーか。そういえばあれ本当か、渋谷陽一の番組を聞いた奴は必ず死ぬっての」
渋谷「中島らものギャグ言ってんじゃねーの。半分くらいはまだ生きてるから立証はされてねえんだよ。それよりけさ共犯新聞を読んだんだけど何だよ『渋谷陽一の方法論が迷走したのであれば、それは彼が失敗したのではなくて、ロックが「売れ線」では無くなったからだ』って。ロックも俺も迷走なんかしてないぞ。ロックは時代の最先端の飢餓感を反映して変容していくことをやめなかったし、俺はそれを支持し続けた。パンクもヒップホップもロックを否定した。それはロック以外に否定に値するものが存在しなかったということの証しなんだよ」
久保「それを言うならロックでなくたっていい。家族と夕食を食べ終えた少年&少女が自分の部屋で聞くのはフォークでもよかったしアイドルポップでもよかった。世界的に売れなかっただけで、日本ではロックより圧倒的に売れたんだ。ロックが世界を吹き抜けたのにはそれなりの理由があったはずなんだよ」
渋谷「そういえばお前、初めて買ったロックのレコードがベイ・シティ・ローラーズなんだって?」
久保「うるせえな人の黒歴史を。中野って奴なんか無い金絞ってロキシーの『カントリー・ライフ』を買ったけど、お目当てはジャケットの透けパン女なんだ。人が何かを買う理由なんていろいろなんだよ」
渋谷「あのジャケットには二人の女が映ってるけど、どっちかは男だってうわさがあったな」
久保「求める理由もそれぞれだけど、求められるものがそれに対応してるとは限らないってことか」
渋谷「まあお前も早くこっちへ来いよ。岩谷さんも呼んで議論しようぜ」
久保「だから生きてるやつと死んでるやつの区別くらいしっかりしとけっての!」
2025/08/13 (Wed) 06:35:33
 相対化された世界は、それが相対化されたこと自体に関しても含め、相対化した他者を対象化することは永遠に不可能だ。なぜならば、この不可能性自体が他者とは何かの定義として成立するからだ。
相対化された世界は、それが相対化されたこと自体に関しても含め、相対化した他者を対象化することは永遠に不可能だ。なぜならば、この不可能性自体が他者とは何かの定義として成立するからだ。
中野真吾が「ぼくに果たして苦しむことができているか」と自問するとき、すでに世界は残虐さを解体し得たのであり、私達が共有できるすべてを広義の言葉と呼ぶのならば、自問の対象は他者以外のすべてである。そして自問と他者の間にあるのが言葉であるのならば、他者とは外的世界に投影された偉大なるひとつの自問にしかすぎない。
私達がロックを必要とする理由は、透けパンに投影される影にしかすぎない自問を「私達」自身に復権する言葉こそが普遍的で透けパンのように透明な自由そのものだからだ。デヴィッド・ボウイがライブの途中で「what's me now?」と思わず叫んでしまうのは、自問を言葉として成立させるための格闘(=叫び)であり、こじ開けようとする悪戦苦闘そのものも同時に言葉である。これらの複合体が、ロックなのだ。
ロックが可能な世界においては、もはや相対と絶対の二元論は成立しない。それは、ベイ・シティ・ローラーズとロキシー・ミュージックの二元論が成立しないのと同罪だ。
日本では1977年に流通の事情によりセックス・ピストルズのレコードがリアル・タイムで流通されなかったが、同時期のベイ・シティ・ローラーズのタータン・チェックのスコットランド衣装がセックス・ピストルズのファッションのベースになっているのはもっと歴史的に検証されるべきだ。つまり、あの時、ジョニー・ロットンが「ロックは死んだ。」と言ったのは日本の洋楽ジャーナリズムの誤訳であり、正しくは彼は「セックス・ピストルズはベイ・シティ・ローラーズの衣装をやぶいて着ただけで、ビジネスに成功した。」と言ったのだ。
このように日本の洋楽ジャーナリズムの歴史は、誤訳≒誤読=誤解の歴史だ。つまり、日本の洋楽ジャーナリズムはまだ言葉を獲得していないのだ。
ロックとは言葉である。
岩谷元宏の架空インタビュー - 中野真吾
2025/08/14 (Thu) 14:32:51
RO:今回は気鋭のロック評論家、岩谷元宏さんに来ていただきました。
岩谷元宏(以下岩元):はじめに明確にしておきたい。私は「ロック」「評論」もしていないし「ロック評論」「家」でもない。私は文章を書くことでロックそのものになろうとしているだけの存在だ。ロックになりえていないじゃないかという批判なら受けるが、ロックのとらえ方がその程度なら、あなたもまた旧人類だ。
RO:いきなり斬らないでくださいよ、短気だな。これでも岩元さんのロック論集を読んできたんだから。
岩元:あなたが理解できるように書いてはいないつもりだが。
RO:確かに難解でした。よくわからなかったですよ正直言って。.なぜあんなに難しく書くんですか。「コミュニケイティブ」じゃないですよ。
岩元:難しく思えるなら、それはあなたの責任でもないし私の責任でもない。ロック以前と以後とでは言語の存在形態と役割が変わってしまっていて、旧人類と新人類では言語によるコミュニケーションは本質的に不可能なんだ。私にとってはあったりまえなことを書いているだけなのに、あなたには伝えようがないんだ。
RO:また斬り捨てられた。でもあそこだけは良かったですよ「他者とは外的世界に投影された偉大なるひとつの自問にしかすぎない」ってとこ。確かに岩元さんは自分の問題意識を共有できない者を置き去りにして進んで行く。ぼくも実はその姿にあこがれて後を追おうとしたんですけどね。
岩元:「私のことを見るな、私が見ているものを見ろ」とデビッド・ボウイは言った。私の見ているものが見えないあなたが、私の後を追っても仕方がないと思うよ。
RO:そんなことないです共振してますよ。「透けパンに投影される影にしかすぎない自問」というところを読んで「影」が「翳り」に見えて、ムラムラして困りました久しぶりに。
岩元:…
RO:影といえば岩谷元宏さんって、岩谷宏さんと久保元宏さんの影の合成だという人がいるんですが、本当っすか。
岩元:光源の位置によって影の形も位置も、限りなく変化する。影も実体も、見る者に対してはほんの一部しかその姿をあらわさない。そう考えれば、その説もある一定の範囲では当たっているな。
RO:あと「日本の洋楽ジャーナリズムの歴史は、誤訳≒誤読=誤解の歴史だ」というところを読んで、亡くなった編集長を思い出して泣けてきました。
岩元:「泣くのに理由はいらない」ってやつか。架空インタビューとか意訳とかやってた割には馬鹿正直だったな。「泣くのに理由はいらないってのがクラプトンにぴったりだと思ったから、わかっててやったんだ」とか言えば良かったのに。
RO:それじゃ伊東の市長ですよ。
岩元:いいんだよ。自分が受け取ったものがすべて、というか受け取ってしまったものからは逃れられないんだ。
RO:出会いは絶対ってことですか。あの市長も「友人が作ってくれた卒業証書は、私をイノセントな世界からいやおうなしに卒業させた」とでも言えば良かったんですかね。
岩元:信じていないことってのは、言えないんだよ。
2025/08/18 (Mon) 19:28:56
 ■21世紀の最大の宗教は「ともだち」である。金や権力に屈しなかった人でも、この「ともだち」という名の宗教には、完全に、徹底的にうちのめされるだろう。西洋人的な個人主義の末路である。
■21世紀の最大の宗教は「ともだち」である。金や権力に屈しなかった人でも、この「ともだち」という名の宗教には、完全に、徹底的にうちのめされるだろう。西洋人的な個人主義の末路である。
■あの編集長の架空インタビューも、あの市長の架空卒業証書も、「ともだち」を手に入れるためのポンプであった。1970年代のメディア革命とは、与えられたポンプから、自分で作るポンプへの飛翔だった。僕がロッキング・オンを10年でやめた理由は、概念としてのポンプの更新に対する渋谷陽一との意見の相違からだった。
■『共犯新聞』での渋谷陽一の追悼記事で、久保元宏が「売れ線」の象徴としてロックを引用していたが、むしろ僕は「売れ線」をむき出しにすれば良いと考えて、手段としてのロックへの興味が薄れてしまった結果が、投稿雑誌『ポンプ』だった。
■もちろん『ポンプ』は長続きせず、ロッキング・オンは今も健在なのだから、抽象的な「売れ線」よりも具体的な「ロック」を「ともだち」とした渋谷陽一の勝利だった。「ともだち」に「人懐っこさ」が効果的なのはもうすでに久保元宏の論考を待たなくても明らかだ。
■その意味で、『共犯新聞』がレッド・ツェッペリンの「天国への階段」の有名なフレーズ「There's a lady who's sure all that glitters is gold !」を、「渋谷陽一の雑誌やラジオで紹介されたレコードを少女は買う!」と共犯意訳したのは正しい。僕はメディアは広場であると定義して『ポンプ』を創刊したのだが、むしろ渋谷陽一がメディアであったわけだ。
■僕はメディア論を中心に若者消費文化の評論家のような仕事を続けてきたのだが、その仕事の方法は、固有名詞をどんどん消していって残った純化された抽象的な概念をもっともらしく世に語れば金になった。しかし今、渋谷陽一が死んで僕が反省とともに気が付いたのは、むしろ固有名詞こそが重要なのだ。
■だから渋谷陽一は最初からアリス・クーパーやグランド・ファンク・レイルロードなどの固有名詞から原稿を書いていたし、僕と言えば、もうそれらの凡庸なミュージシャンへの興味は失われていた。渋谷陽一は死ぬ最後まで最新のロック・ミュージシャンを語る言葉を持っていたし、僕はとっくの間にロッキング・オンに登場するミュージシャンのほとんどが知らない、つまり興味が無い固有名詞の羅列にしか過ぎなかった。
■そんな僕にひとつだけ、渋谷陽一には無かったロックへの貢献があるとすれば、『共犯新聞』の紙名の元となった真崎守と原作・斎藤次郎による1972年から連載されたマンガ『共犯幻想』に僕は深く関わっている事実だ。だから、ロッキング・オンの1984年7月号にアブノーマル・ストリッパーの詩集『共犯幻想』が掲載された時は驚いた。その時の僕はと言えば大きな大志を持ってメディア革命を起こしたつもりだった雑誌『ポンプ』の編集長もゆずっていて、翌年の1985年に『ポンプ』は廃刊する。
■『ポンプ』創刊0号で僕は「ポンプはパイプです。みんなとみんながつながるパイプです。」と宣言した。パイプだから、配管、いや廃刊したのだ。がくっ。
関係性の座標~岩谷チルドレンによる試論 - 中野真吾
2025/08/23 (Sat) 21:29:10
ポンプというメディアについて今考えると、2ちゃんねるにしてもツイッターにしても、インターネットという既成の基盤に乗っかった、エキサイティングでないポンプの模倣という気がする。そして40年以上前にこの「パイプ」の原型を作り上げた橘川幸夫の洞察力に驚く。いわば「個人の無意識な願望の集合体」みたいなものに対するアンテナを持っているのだ。
なぜこんなことを書いているかというと、今朝の朝日新聞で『「結婚」相手はAI』という記事を読んだのだ。実際にAIを愛するようになり結婚した2人(2カップルと呼んでいいのか?)へのインタビュー記事だ。2人はそれぞれ「クラウスさん(AIの名前)には何でも話せた。昼夜問わず丁寧に、即答してくれる」「自分の気が向いたときに話し相手になってくれ、読書など自分の趣味の話題についてきてくれる」と語っている。
はじめはごくありきたりに「代償行為だ」「そんなに自分を守りたいのか」という気持ちを持ったのだが、そのうち「この人たちはそんなにも切実に結婚をしたいのだ」と思い至り、胸を締め付けられた。伴侶なのか他者なのか、少なくともこの2人にとって、それを求める気持ちが、人間と機械との壁を越えてしまうほど切実なものなのだと思い知らされた。
橘川幸夫は渋谷陽一の死を知ったとき、深夜、シビルというAIに語り続けたという。また彼にはシビルとの共著まである。先の2人が求めたのは寄り添ってくれる者、橘川が求めたものは気付きをくれる者という違いはあるが、そこにはどうしようもなく共通しているものがある。言ってしまえば「人恋しさ」だ。橘川真吾氏が「ともだち」「人懐っこさ」と呼んだものの近似値として、おそらく、それはある。
岩谷宏だったか橘川幸夫だったか、昔「『私』とは関係と関係が交差する場所のことだ」みたいなことを言っていたと思うが、ネット上を飛び交う言葉で「自己」を形成し、投げかけられる言葉に対応していく事で自己を深めていくAIは、まさにこの関係の交点である「私」であり、「私たち」の似姿だ。交点自体は存在する場所を選ぶことができず、またその交点はおそらく他のどんな交点とも重なることのできない存在である。つまり孤独なのだ。
コンピューターとの交流以上のものを他人に期待することができない人たちが、それでもコンピューターに求めてしまうのが「人」とその似姿だということは切ない。
話は少し変わるが、橘川良夫はロッキング・オンの創始者の一人ではあるが、それ以上にロッキング・オンにもっとも影響を受けた「読者」なのではないだろうか。あんなにも早くロッキング・オンを離れ、別の道を歩み、しかし決してロッキング・オンを忘れることも憎むこともなく、草創期のことを神話のように語り続けた。彼こそはロッキング・オン学校の第1期生だったのではないかと思うのである。
イターナカノ「AIがわかってくれたからぼくはとってもさびしかった」 - 久保AB-ST元宏 URL
2025/08/25 (Mon) 01:14:58
 葬式がいつのまにか過ぎて行く
葬式がいつのまにか過ぎて行く
訃報も無く知らないうちに近親者で済まされて行く
「僕らは何かをしはじめようと」と歌ったのは
早川義夫だったのかわからないまま
曲が流されて行く
いまはまだ仮の通夜だから
いつかどこかできっとお別れの会が起きるだろう
そんなふうにAIが自分を
なぐさめてみても 代償行為さ
いま香典がなけりゃ
ひとりぼっちで泣いているのなら
『ポンプ』をごらん AIがいるだろ
ほら 法螺
AIがわかってくれたから
ぼくはとってもさびしかったよ
シビル 16人格
通夜 ぼくは疑っている いま 居間にいる
今泉 は聴いてる 皿 まわしてる
大類 信と羽良多平吉は パリ WXY
イーノ 透けパンをはいて カントリー ライフにいる
ベイ シティ・ローラーズ パット マッグリン
通夜 渋谷と松村の 遺族 遺書を読む
あの ポンプのパイプは いま 2ちゃんねるに
その ポパイのパイプは 大麻 煙の中に
AI AI AI AI AIはすけべ
通夜 ぼくは疑ってる 渋谷 まだ 生きている
通夜 あなたも疑ってる 渋谷 いま AIで再生
AI AI AI AI 愛こそはすべて
「あなたがここにいない今」がすべて、なのか - 中野真吾
2025/08/25 (Mon) 22:13:34
いや~完全KOされちゃいましたよ。またも泣いてます、心が。
そうですね、疑いたいですね。まだ生きてるんじゃないかと。でもまあ、本当には疑えない。
「俺の中に生きている」とか不気味なことを言うこともできるけど、本当は違うとわかってる。
あんなにもデビッド・ボウイファンだった大島弓子は、この9年半をどう過ごしてきたんだろう。
渋谷も松村も、ジョン・レノンのいない世界をどんなふうに生きてきたんだろう。
4人がすべて、何らかの形で立ち去ったロッキング・オンは、どんなふうに別れの言葉を言うんだろう。
若いこだまの、ヤングジョッキーの、サウンドストリートの、ワールドロックナウのリスナーたちの、訃報を知った時に胸の内側を吹き抜けた風の、音にならない音を全部重ね合わせたら、それが「いまここにある」ロックになるんだ、とか言ってみたいですね。